はじめに
「研究者って、どんな人たちなんだろう?」
昆虫学者・前野ウルド浩太郎さんの著書『バッタを倒しにアフリカへ』は、そんな素朴な疑問に対して、驚きと感動、そして笑いと少しの哀愁をもって応えてくれる、異色のノンフィクション作品です。
私は医療・生物系の研究に携わる立場として、実験や論文、研究費との格闘の中で日々を送っていますが、この本にはそれらの苦悩すら小さく思えるほど、圧倒的な現場感と情熱が詰まっていました。そして読み終えた後には、胸が熱くなり、「自分もまだやれる」と自然と前を向けるような力をもらえました。
ここでは、そんな一冊を時系列に沿ってご紹介しつつ、研究者という職業のリアルや、夢を追い続けることの大切さについて綴っていきたいと思います。
ストーリーについて
昆虫少年、ファーブルに憧れる
前野浩太郎さんは、子どもの頃から昆虫、とくにバッタに強い興味を持っていた少年でした。きっかけは『ファーブル昆虫記』。この一冊に触発され、彼は「将来は昆虫学者になりたい」と真っすぐな夢を描きます。そしてその夢を、周囲の期待や社会の常識に左右されることなく、大人になっても持ち続けるのです。
神戸大学大学院からアフリカ・モーリタニアへ
大学進学後は昆虫学の道を選び、神戸大学大学院で博士号を取得。研究対象はサバクトビバッタ。これはアフリカを中心に蝗害(こうがい)を引き起こす深刻な害虫で、農作物を一晩で食い荒らしてしまうほどの脅威です。昆虫学としての興味だけでなく、食糧問題への貢献という社会的意義のあるテーマを彼は追いかけていました。
しかし、博士号を取ったあとも日本では研究職のポストに恵まれず、「現地での研究実績を作るしかない」と考えた前野さんは、単身でアフリカ・モーリタニアの「国立バッタ防除センター」へ渡る決意をします。これは、普通の研究者ならなかなか踏み出せない大きな決断です。
モーリタニアの現実:文化・言語・生活の壁
現地では、まさに“異文化”との戦いが待っていました。フランス語が共通語であるモーリタニアにおいて、前野さんは言葉の壁にまずぶつかります。加えて、約束の時間に人が来ない、装置が壊れる、郵送トラブルが頻発するといった、日本の研究環境では考えられないような事態が日常茶飯事でした。
さらに追い打ちをかけるのが「肝心のバッタがいない」という問題。干ばつによってバッタの群れが姿を消し、サンプルが取れない状態が続きます。研究どころか、存在意義すら問われかねない状況のなか、それでも彼は腐らず、「バッタに食べられたい」という夢まで語りながら、日々を前向きに生き抜いていきます。
仲間との出会いと文化の交差
そんな前野さんを支えるのが、現地スタッフのティジャニ。最初はうまく意思疎通もできず、文化の違いに戸惑いながらの関係でしたが、次第に信頼を築いていきます。二人は共に汗を流し、バッタを追い、笑い合い、励まし合う仲間になっていきました。
さらに、現地で「ウルド」というミドルネームを授かるという出来事もありました。これは現地社会での受け入れの証であり、前野さんの誠実な姿勢と研究への本気度が伝わった証拠でもあります。
感想
前野さんの生き方は、「研究者とはかくあるべし」という型にはまったイメージを大きく覆してくれます。研究のためにアフリカに飛び、自ら泥をかぶってでもフィールドに出続ける姿勢。それは論文の数やインパクトファクターといった数字では語り切れない、“覚悟”そのものです。
私は医療・生物系の研究に関わっていますが、前野さんのように現場に根ざした研究者の姿には、憧れすら感じました。
現代の日本では、特に進学校や医学部で「良い大学に入ること」が目的化され、その先にある「自分が何をやりたいか」「何のために学ぶのか」という視点が見えにくくなっているように感じます。もちろん受験や進路も大事ですが、本書のように“夢”を持ち続け、それを行動に移す生き方は、あらためて学びの本質を問いかけてくれます。
また、著者の語り口にはユーモアと人間味があり、重たい話も自然と読み進められる工夫がなされています。研究の苦労だけでなく、笑える失敗談や夢物語まで交えて語られることで、「研究者も一人の人間なのだ」と実感させられ、強い親近感を持ちました。
まとめ
『バッタを倒しにアフリカへ』は、研究者だけでなく、何かに夢中になったことのあるすべての人に読んでほしい一冊です。
子どもの頃の好奇心を大人になっても失わず、現地に飛び込んででも夢を追う。その姿勢は、研究に限らず、あらゆる分野で生きる人々にとってのヒントになるでしょう。
● なぜ学ぶのか迷っている学生さんへ
● 日々の研究や仕事に疲れてしまった社会人へ
● 子どもの教育に悩む親御さんへ
この本を読むことで、「夢中になること」の価値、「信念をもってやり続けること」の意味を、あらためて実感できるはずです。
私自身も、この本を子どもに勧めたいと思っています。そして、自分自身も泥まみれになりながら“本気で何かを追う研究者”でありたい。そう強く思わされた一冊でした。
最後に、こんな冒険と情熱の物語がベストセラーになったという事実こそ、今の日本社会にとって大きな希望ではないでしょうか。いつか著者の講演に参加して、直接その声に触れてみたい——そんな新たな夢すら、この本は与えてくれました。
「バッタに食べられたい」——奇妙に思えるこの一言の奥に、研究者としての誇りと、夢を生きる覚悟が宿っています。あなたもきっと、ページをめくる手が止まらなくなるはずです。

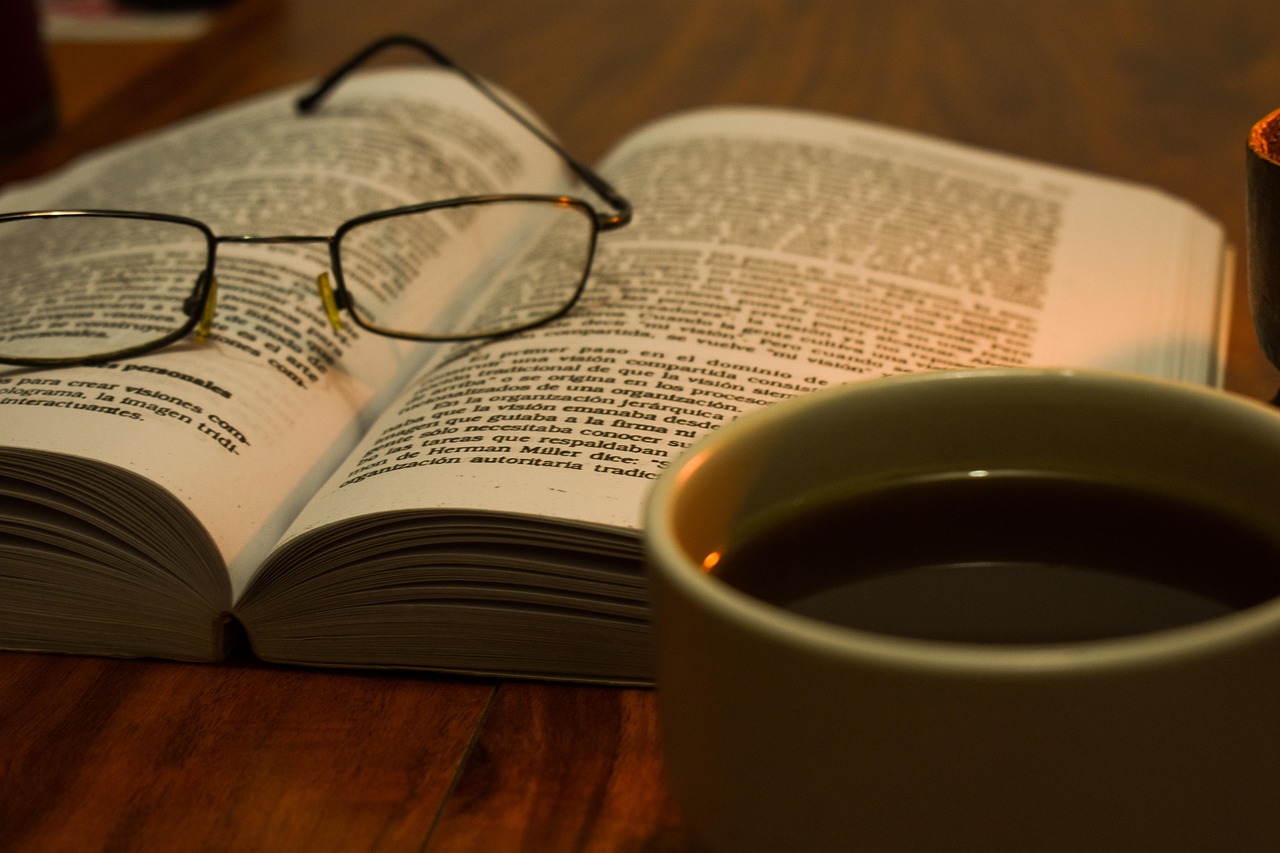


コメント