はじめに
「低置胎盤」は前置胎盤ほど重篤ではないものの、出血リスクや帝王切開の判断、癒着胎盤・前置血管の併発など、臨床判断が求められる重要なテーマです。
この記事では、産科ガイドラインCQ305に沿って、要点をわかりやすく整理・解説します。
低置胎盤とは?その診断基準
定義
- 超音波診断において胎盤下縁が内子宮口から2cm以内にある状態。
- 前置胎盤との違いは、子宮口を“覆っていない”点。
診断のタイミング
- 胎盤は妊娠後期に**“上がる”こと(placental migration)があるため、確定診断は妊娠36〜37週ごろ**。
- ただし、分娩直前の診断は難しいため、子宮口開大前の経腟エコーで判断するのが実用的。
分娩様式の決定
経腟分娩 vs 帝王切開
胎盤下縁と内子宮口の距離と経腟分娩の成功率:
- 20mm以上 → 82%の成功率
- 11〜20mm → 85%
- 0〜10mm → 成功率43%
このように、距離が近いほど経腟分娩のリスクが高くなるため、距離と患者状態、施設体制をもとに帝王切開も考慮します。
前置血管の併発に注意!
前置血管とは?
- 胎盤から出る臍帯血管が、内子宮口の前を無防備に走行している状態。
- 破水や陣痛で容易に断裂し、胎児の死亡率56%に及ぶことも。
なぜ低置胎盤で併発しやすい?
- 胎盤の形状異常(分葉胎盤や退縮)により、内子宮口付近に血管が迂回するケースが多いため。
対応策
- カラードプラで必ずスクリーニング。
- 前置血管がある場合は必ず帝王切開を選択し、破水前の分娩が重要。
癒着胎盤のリスク
リスク因子
- 子宮前壁付着の低置胎盤かつ
- 帝王切開の既往がある場合
この組み合わせは癒着胎盤のリスクが非常に高い。
管理の工夫
- 術前にMRIや超音波で癒着の評価
- 出血対策として輸血準備、子宮全摘も選択肢に。
- CQ304の「前置胎盤管理」と同様に、多診療科連携が望ましい。
分娩後の出血にも注意
- 子宮下節に付着した胎盤は、生理的な止血(血管の収縮・血栓形成)が効きにくい。
- 経腟でも帝王切開でも、分娩後の異常出血リスクは前置胎盤と同様に高い。
対応策
- 出血時は、以下のような即時対処が重要:
- 双手圧迫
- 圧迫縫合
- 子宮収縮薬
- バルーンタンポナーデ
問題
32歳、2経妊1経産。妊娠36週の妊婦健診で、胎盤の下縁が内子宮口から9mmに位置する低置胎盤と診断された。胎児は逆子ではなく、これまで出血はない。妊婦は経腟分娩を希望している。次にとるべき対応として最も適切なのはどれか。
A. 陣痛発来まで待機し経腟分娩とする
B. 前置胎盤ではないため自然分娩とする
C. 分娩前にMRIで癒着胎盤の有無を確認する
D. 胎児心拍モニタリングで異常がなければ経腟分娩とする
E. 帝王切開を含めた分娩方法を医師と相談し決定する
正解
E. 帝王切開を含めた分娩方法を医師と相談し決定する
解説
- 胎盤下縁が内子宮口から9mmという所見は、経腟分娩可能性があるがリスクも高いグレーゾーン。
- 距離が0〜10mmの場合の経腟分娩成功率は43%程度と低下しており、必ず分娩様式を慎重に検討する必要がある。
- よって「相談と合意を得て分娩方針を決定する」姿勢が推奨される。
- 単に自然分娩を許容する、あるいはMRIをルーチンに行う選択肢は不適切。
まとめ
低置胎盤は、胎盤の位置だけでなく、前置血管や癒着胎盤、出血リスクまでを総合的に判断して管理する必要があります。
管理のポイント
- 診断は妊娠36〜37週の経腟エコーで最終判断
- 2cm以内なら低置胎盤、分娩様式は個別に検討
- 前置血管・癒着胎盤の有無も見逃さない
- 分娩後も異常出血に備え、体制を整える
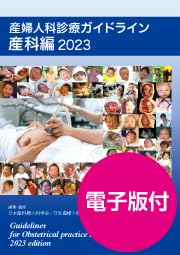
【楽天市場】産婦人科診療ガイドライン 産科編 2023 杏林舎 ボールペン付き 日本産科婦人科学会:エッセンシャルショップ
産婦人科診療ガイドライン 産科編 2023 杏林舎 ボールペン付き 日本産科婦人科学会

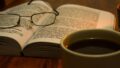

コメント