はじめに
「どうしてあの人の評価ばかり気にしてしまうんだろう?」 「やりたいことがあるのに、誰かの顔色をうかがって動けない……」
そんな悩みを抱えていた私にとって、アドラー心理学との出会いは、人生の転機となるものでした。 きっかけはベストセラー『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著)との出会いでした。
今回は、私自身の体験を交えながら、『嫌われる勇気』を中心にアドラー心理学のエッセンスをかみ砕いて解説します。 心理学に詳しくない方にも読みやすいよう、できるだけ身近な例や実生活への応用も紹介していきます。
アドラー心理学とは?
アドラー心理学は、20世紀初頭にオーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学の体系です。
フロイトやユングと並ぶ「心理学三大巨頭」の一人でありながら、日本では長らくそれほど知られていませんでした。 しかし、近年『嫌われる勇気』の大ヒットによって、一般にも広く知られるようになりました。
アドラー心理学の最大の特徴は「原因論」ではなく「目的論」に立って人の行動を解釈することです。 つまり、「なぜこんな性格になったか(過去)」ではなく、「どう生きたいか(未来)」を重視します。
『嫌われる勇気』に描かれたアドラーの教え
『嫌われる勇気』は、青年と哲人の対話形式で進む哲学書でありながら、非常に読みやすくエンタメ性もあります。 その中で紹介されるアドラー心理学の核となる概念は、以下のようなものです。
- 課題の分離
- 承認欲求を捨てる
- 劣等感と劣等コンプレックス
- 共同体感覚
- 自由とは他者に嫌われることである
それぞれ私の経験とともに解説していきます。
課題の分離:誰の課題かを見極める
かつての私は、「上司がどう思うか」「親が反対しないか」「友人が引かないか」など、他人の反応ばかりを気にして行動できない人間でした。
でも、アドラー心理学ではこう教えます。 「それは誰の課題か?」
例えば子どもが勉強しないとき、親はつい「勉強しなさい」と言いたくなります。 しかし「勉強するかどうか」は子どもの課題。 親ができるのは「学びやすい環境を整えること」だけ。
他人の課題に踏み込んでしまうと、支配か、依存が生まれます。
私も、「あの人にどう思われるか」を気にしていたのは、実は「相手の課題」に踏み込んでいたということに気づきました。
承認欲求を捨てる:評価されたい自分を手放す
アドラーは、「他者から承認されたいという欲求は不自由の根源である」と言います。
たとえば、SNSの「いいね」が気になって何度もスマホをチェックする。 仕事で「上司に褒められるため」に努力する。 これらは、すべて他者の評価を自分の行動の軸にしている状態です。
私も以前は、周囲の期待に応えることばかり考えて疲弊していました。 でも、自分の行動の目的を「自分がそうしたいから」と明確にしたとき、他人の評価に振り回されなくなりました。
承認欲求を手放すことは、「自由になる」ことでもあるのです。
劣等感と劣等コンプレックス:劣っていても、問題ではない
私たちは、誰もが何らかの「劣等感」を抱えて生きています。 アドラーは、劣等感を「成長のための刺激」として肯定的にとらえました。
問題なのは、劣等感を理由に行動しない「劣等コンプレックス」に陥ることです。
「私は話すのが下手だから発言しない」 「人見知りだから新しい環境が苦手」
これらはすべて、「劣等感」を言い訳にして課題から逃げている状態です。
かつての私もそうでした。でも、「下手でもいいから、やってみよう」と思った瞬間、世界が変わりました。
共同体感覚:自分の幸せは、誰かの幸せとつながっている
アドラー心理学の最終的な目標は「共同体感覚」です。 これは、自分を社会の一部としてとらえ、「他者への貢献感」を得ている状態を指します。
私も「誰の役に立っているかわからない」と悩んでいた時期がありました。 でも、家族との時間、仕事でのちょっとした助け合い、SNSでの励ましのコメント——そんな小さな貢献が「生きていてよかった」と思える感覚につながりました。
他者のために生きる、ではなく「ともに生きる」感覚。 それが共同体感覚です。
自由とは「嫌われる勇気」を持つこと
『嫌われる勇気』というタイトルは衝撃的ですが、これは「人を傷つけろ」と言っているのではありません。
「他人にどう思われるかを気にして自分を偽るのではなく、自分の信じる生き方を貫く勇気を持て」という意味です。
もちろん、誰にも嫌われたくないと思うのが人間です。 しかし、すべての人に好かれようとすれば、誰のことも幸せにできません。
私は、「すべての人に好かれなくてもいい」と思えるようになってから、逆に人間関係が楽になりました。 無理に取り繕わず、ありのままの自分でいることで、深い信頼関係が生まれることもあります。
アドラー心理学を日常に活かすには
- まずは「これは誰の課題か?」を意識する
- 自分の行動の目的を問い直す:「やらねば」ではなく「やりたいか」
- 小さな貢献に気づく:笑顔、挨拶、ありがとう
- 他人の評価に反応する前に、「自分の基準」を持つ
- 嫌われる勇気を、少しずつ練習してみる
まとめ
アドラー心理学は、特別な才能が必要な理論ではありません。 むしろ、「普通の人が、よりよく生きるための考え方」です。
私は、『嫌われる勇気』を通じて、自分の人生を他人に委ねるのではなく、「自分で選び、自分で責任を持つ」生き方に切り替えられました。
最初は不安もありましたが、それ以上に「自由と幸福感」を感じられるようになったのです。
誰かの目が気になって仕方がない人、 いつも他人の顔色をうかがってしまう人、 自信がなくて一歩が踏み出せない人——。
そんなあなたにこそ、『嫌われる勇気』とアドラー心理学を届けたいと思っています。
最後に、私が勇気をもらった言葉を贈ります。
「あなたがどんなに立派なことをしようとも、必ず非難する人がいる。 だから他人の評価ではなく、自分の目的に従って生きなさい。」
一歩踏み出す「勇気」を、あなたにも。

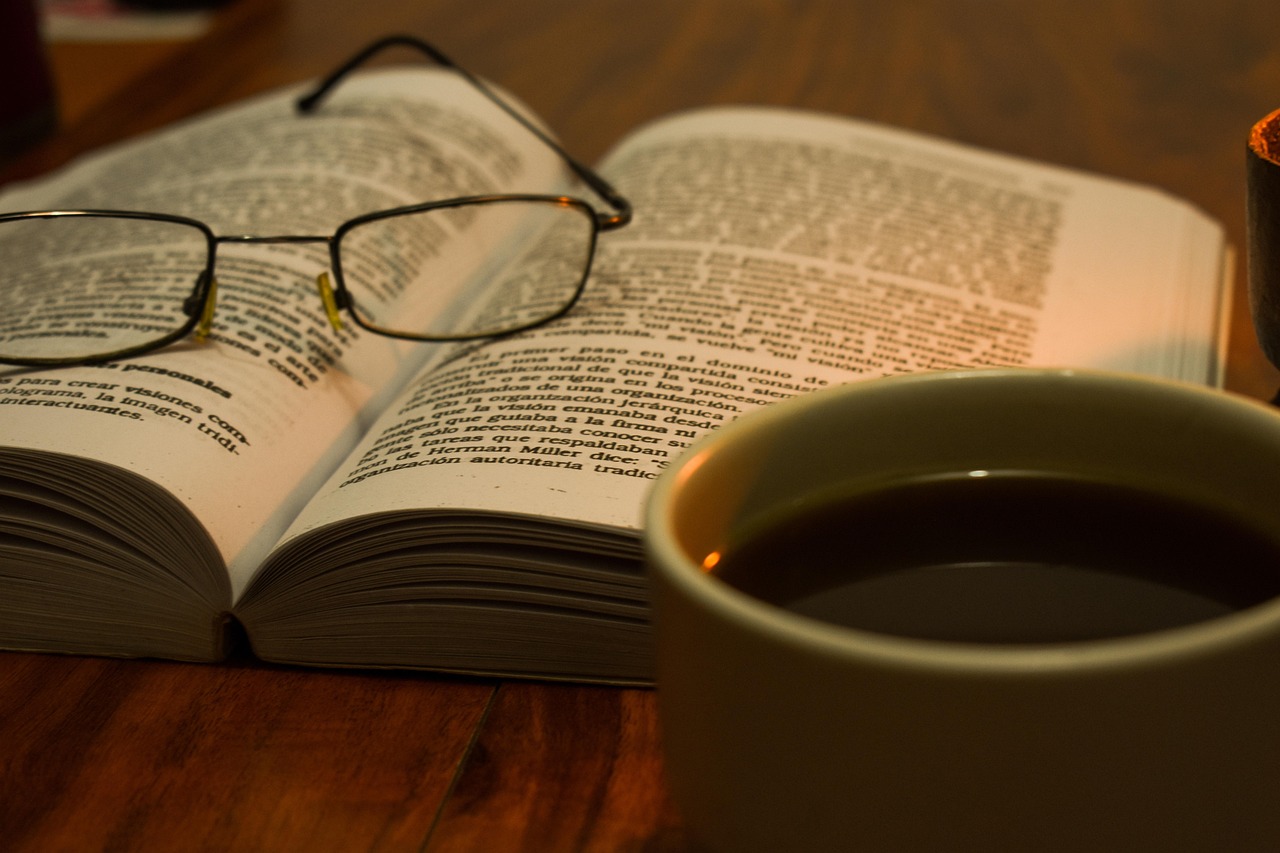


コメント