はじめに
妊婦健診で行う超音波検査において、胎児の発育評価は欠かせません。今回は「CQ106-4:胎児計測(BPD,AC,FL)で異常を疑った場合の対応」について、ガイドラインに基づいた解説をお届けします。
胎児計測の基本項目
胎児の発育状態を把握するうえで重要なのが以下の3項目です:
- BPD(児頭大横径)
- AC(腹囲)
- FL(大腿骨長)
これらの値を用いて**推定胎児体重(EFBW)**が算出され、発育の正常範囲かどうかが評価されます。基準値としては、日本超音波医学会の2003年基準が使用されるのが一般的です。
異常を疑ったら確認すべきポイント
胎児計測で異常を認めた場合、以下のステップで対応を考えます。
1.異常値の判定には基準値と経時的評価が必要
- 計測値が**±1.5〜2.0SDを超える場合**に「異常」と判断されることが多いですが、これはあくまで目安。
- 発育曲線上で経時的な変化を確認することが非常に重要です。
- また、両親の人種的背景によって国際基準チャート(WHO基準)を参考にすることもあります。
2.原因検索のための3ステップ
2-1:母体要因の評価
- 基礎疾患や合併症(糖尿病、甲状腺疾患、精神疾患など)
- ライフスタイル要因(喫煙、飲酒、BMI)
- 妊娠中の合併症(妊娠高血圧症候群、感染症など)
2-2:胎児側の異常を評価
- 各部位の計測異常から疑われる疾患を整理:
| 計測部位 | 疑うべき異常 |
|---|---|
| BPD異常 | 水頭症、無脳症、頭蓋内奇形など |
| AC異常 | 腹壁破裂、臍帯ヘルニア、胸腹部疾患など |
| FL短縮 | 骨系統疾患、染色体異常(21トリソミーなど) |
2-3:高次施設への紹介
- 明らかな異常や精査が必要と判断された場合は、母児管理が可能な周産期センターなどへ紹介します。
補足:胎児発育不全(FGR)との関連
胎児計測の異常は、FGRのスクリーニングにもつながります。詳細はCQ307-1、CQ307-2を参考にするとよいでしょう。
問題
妊娠28週の妊婦健診で、超音波検査により胎児のFLが−3SD、BPD・ACは正常範囲であった。次に行うべき対応として最も適切なのはどれか。
A.染色体検査のための羊水検査を直ちに行う
B.母体の体重管理と経過観察のみでよい
C.胎児の他部位に形態異常がないか詳細な超音波検査を行う
D.新生児科医に出生後の対応を依頼する
E.NT値を再評価する
正解
C.胎児の他部位に形態異常がないか詳細な超音波検査を行う
解説
FLのみが著しく短縮している場合、骨系統疾患や染色体異常の可能性がある。まずは、他部位に異常がないか評価し、形態異常や合併疾患の有無を確認することが優先される。
Aは確定診断目的の検査だが、まずは形態評価を優先。
Bは根拠に乏しく不適切。
Dは出生前対応としては時期尚早。
EはNT値評価の適応外(妊娠11〜13週が測定時期)である。
まとめ
胎児計測に異常が見られた際には、以下の観点から対応を考えましょう:
- 基準値と経時変化から発育異常を判断
- 母体と胎児両面からの原因精査
- 必要時には高次施設への紹介
知識だけでなく、チーム医療の視点も忘れずに判断できるよう心がけましょう。
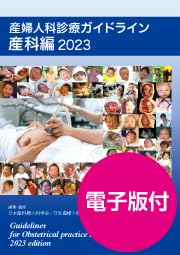

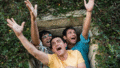

コメント