はじめに
出生前検査は、胎児の染色体や遺伝子の異常を出生前に評価する重要な手段です。しかしその一方で、検査の種類や意義、対象疾患、倫理的側面まで幅広く理解が求められます。
今回は「CQ106-5」を題材に、出生前の染色体検査・遺伝子検査を行う際の注意点について、研修医や医学生向けにわかりやすく整理してみましょう。
1. 遺伝カウンセリングとインフォームドコンセントが基本
出生前に染色体や遺伝子の検査を行う場合には、必ず遺伝カウンセリングを行ったうえでインフォームドコンセント(IC)を得る必要があります。
このカウンセリングでは以下のような内容が含まれます:
- 家族歴の聴取
- 検査の意義や方法、有害事象の説明
- 異常が見つかった場合の対応や予後
- 支援体制(小児科、患者会の紹介など)
カウンセリングは、産婦人科医だけでなく、小児科医や臨床遺伝専門医・遺伝カウンセラーと連携することが望まれます。
2. 検査の種類と特性
出生前の検査は大きく分けて確定的検査と非確定的検査に分類されます。
確定的検査(診断が確実にできる)
- 羊水検査(15週以降)
- 絨毛検査(11〜14週)
- 臍帯血検査
→ 染色体異常や遺伝子異常の診断が可能。
ただし、流産リスク(0.1〜0.3%程度)があり、侵襲的検査となる点に注意が必要です。
非確定的検査(診断はできず、あくまでスクリーニング)
- 胎児超音波検査
- 母体血清マーカー検査
- NIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)
→ 疾患リスクを推定する検査であり、陽性=確定ではないため、最終的には確定的検査が必要です。
3. NIPTの特徴と注意点
NIPTは母体血中に含まれる胎児由来のcell-free DNAを解析する検査で、対象疾患は「21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー」の3つに限定されています(2023年4月現在)。
- 陰性的中率は99.9%以上と高いが、陽性的中率は妊婦の年齢などで変化(21トリソミーで約96.5%、13トリソミーでは63.6%)
- 陽性でも確定診断には羊水や絨毛検査が必要
- 偽陰性もあり得るので、NIPTで陰性=安心とは限らない
また、NIPTは日本医学会の認定施設でのみ実施可能であり、認定施設以外での実施や紹介には注意が必要です。
4. マイクロアレイ解析などの網羅的検査の扱い
最近ではマイクロアレイ解析などにより、より細かい遺伝子変化(微細欠失やコピー数多型など)の検出が可能になっています。
しかし、意義が明確でない異常を見つけることもあるため、判断には慎重さが求められます。
また、均衡型転座や逆位のように、ゲノム量の変化を伴わない異常は検出できない点も理解しておきましょう。
5. 倫理的な配慮と制度的対応
出生前検査は、「誰でも受けるもの」ではなく、個別に慎重に判断されるべきものです。
マススクリーニング的に推奨することはノーマライゼーションの観点から避けるべきとされ、日本医学会の「NIPT等の出生前検査に関する指針」でも明確に規定されています。
問題
35歳初産婦が妊娠12週で来院し、出生前診断を希望している。
染色体数的異常のスクリーニング目的で非侵襲的検査を受けたいとの希望がある。
このとき適切な対応として最も正しいのはどれか。
A. NIPTで陰性であれば確定診断は不要であると説明する
B. NIPTは母体年齢にかかわらず陽性的中率は一定であると説明する
C. 確定診断としてNIPTを案内する
D. NIPTの結果にかかわらず、羊水検査を行う
E. NIPTは21・18・13トリソミーに限って対象とされていると説明する
正解:E
解説:
- A:NIPTは非確定的検査であり、陰性でも確定診断はできません。×
- B:陽性的中率は年齢によって変化します。×
- C:NIPTはスクリーニングであり、確定診断ではありません。×
- D:NIPTの結果を踏まえて確定診断の要否を判断するため、一律に羊水検査を行うのは不適切。×
- E:日本におけるNIPTの対象疾患は21・18・13トリソミーに限られている。〇
まとめ
- 染色体・遺伝子検査の前には遺伝カウンセリング+ICが必須
- NIPTは非確定的検査であり、あくまでスクリーニング
- 対象疾患や施設の制限に注意
- 網羅的遺伝子解析には判断の難しさも
- 倫理的配慮を踏まえた制度設計が進んでいる
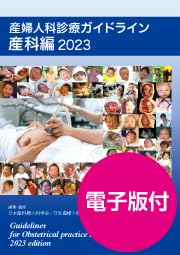



コメント